ボヤけているからこそ神話でありロマンなのだ
まあ研究でピントを合わせて初めて歴史として扱えるのだが
近代で中央同質化を推奨促進し方言を駆逐
日本は単一民族国家で日本民族だとぬかすキチゲエも沸いてきた
人種と民族の区別がつかないバカ
万世一系のとか皇国史観やら
造られた神話がそこら辺を捻じ曲げてるわな
日本式民族浄化だよこれ
アイヌも浄化されちゃった
クマソ、エミシやら多分他にもたくさん
記録には残っていないが列島内には多くのクニがあった
統合の過程で消えた民族が沢山あるのだ
古代から征夷大将軍、珍的将軍として東へ西へ異民族を駆逐する軍を送り込んで民族浄化
部分的には入植の過程でそんなコトもあったかもしれないが、日本人のY染色体の多様性は科学的に証明されている。全体的に民族浄化の歴史ではなかった。
そもそも集団で稲作やる連中と食糧を漁労採集に頼ってる連中では人口の増え方がまるで違う。あとは入植者が持ち込んで来た疫病でネイティブが自然淘汰というのもあっただろう。
おまえ珍的将軍や征夷大将軍や鎮西将軍を舐めんなよ
徳川家康も征夷大将軍だぞ
古臭い説を抜かすな
日本語の上げ下げがアイヌ語のヤンケサンケだ
こんなのが雲霞の如くある
比較言語学が政治にまみれてるというのは世界的に言われる問題で
日本語アイヌ語無関係説も自虐史観の産物にすぎない
日本が本格的な対外危機に見舞われた時代が日本書紀が編纂された時代と明治維新だからだろ
そうやって纏めあげて共同幻想を作る必要があった
アボジ、モンゴル語らしき方言ある、じー?
ほらよ!🇲🇳お父さんだぞ😂🙊🤣

お父さんにかー!!
ばってん、英語らしき方言あるばい!
アジアに🇬🇧イギリスいたんかよwwww
殺人現場もわからずに殺人捜査してるようなもんだぞw
比羅夫が来たのは余市説というのが結構あって
渡嶋自体は元々往来していたので
比羅夫がもっと踏み込んで進んだなら
少なくとも道南を越える必要がある
それならエゾが北方民と沈黙交易していた余市あたりまでは来たのではないか
というのが主旨だ
そして比羅夫の時代でそこまで来ているなら
中世はもっと先に行っててもおかしくない
すでに樺太までは行っていたのではないだろうか
どうもアイヌ単独でそこまでモンゴルとやり合ったというのが気になる
それは津軽安藤氏が加勢したのでは
初代の国王は天御中主と名乗り、彦瀲に至るまで、およそ三十二代とされている。
彼らは皆、尊を尊称として、筑紫城に存在していた。
これは、
後漢皇帝から左将軍に任命された公孫氏が帯方郡を設置して、帯方郡の支配下に置いた
北部九州の倭奴國、漢委奴国王
公孫氏が魏に対して反乱を起こしたあとは
狗奴國、その男王卑弥弓呼
に確定している
https://i.imgur.com/ROn3cpa.jpg


もうタイムマシンが完成しなきゃわかんないんだろうけど
タイムマシンの研究って今でも誰かしてるのかな?もう誰もしてない?
アイヌはモンゴルと戦う際に大陸まで乗り込んでるからな
あまりに強力だ
あの時代にモンゴル相手にそこまでやる奴がいるのか
既に古代天文学で日食の日時は特定されてる、ころされたのは付近の日時だろうな
すごい、
野菜無人販売みたいw
支那人にできるのか??
卑弥呼といえば
私が青春時代にお世話になったav女優を思い出すなぁ
mRNAワクチンを接種しちゃった人たちの130万人が急死したってマジっすか?
支那王の遺伝子改竄が目的?
日本語で”親”と”老い”は同じ語源から来ている
だが中国語のシンとロウは全く別の意味の言葉
訓読みだから一致する言葉
そしてアイヌ語の”オンネ”はちょうど”親”と”老い”両方の意味を持つ
このようなものはかなり古い段階で語彙が共有されていることの表れ
but then
by
なのか!!
言語比較
わたし われ わい 俺 自分不器用ですから
アイヌ カニ
初代の国王は天御中主と名乗り、彦瀲に至るまで、およそ三十二代とされている。
彼らは皆、尊を尊称として、筑紫城に存在していた。
これは、
後漢皇帝から左将軍に任命された公孫氏が帯方郡を設置して、帯方郡の支配下に置いた
北部九州の倭奴國、漢委奴国王
公孫氏が魏に対して反乱を起こしたあとは
狗奴國、その男王卑弥弓呼
に確定している
卑弥呼は、その
北部九州の倭奴國、漢委奴国王
公孫氏が魏に対して反乱を起こしたあとは
狗奴國、その男王卑弥弓呼
の元から、熊野を治めろと追い出された
天照大神
そもそも卑弥呼なんて人物いたかも怪しい
中国発でしょ
そもそも陸地あったの?
なんども海に国土が沈む話出てこねえか?
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E5%BC%8F%E6%B5%B7%E5%B2%B8
印象的な山が多いよね支那って
海に沈んでたから?
誅伐された田油津媛だろ
ではなぜ日本語とアイヌ語の類似性が見落とされて来たか
それは英語でいうリエゾンのような音韻変化の対応があったから
日本語のtはアイヌ語のr
日本語のyはアイヌ語のh
のような感じ
これは中国漢字の中国音と日本の音読みの変換などにもあるもの
nは”ん”だが、ngは長音になったりするように変換に規則性がある
方言内でも関東弁で ai → e; などがある
この地域差が出すぎて元の語句との繋がりがわからなくなってしまった
薩摩地方は郷によって言葉が変わりすぎて意思の疎通も困難だというが?
分かるか?鹿児島にはかつて熊襲と阿多隼人と大隅隼人と違う民族が同居してた名残だよ
日本語には和名抄が成立した西暦930年代まで
nやngの発音が無かったことが確実
平安貴族の女性や一般庶民が「ん」を発音できるようになったのは
平安末期から鎌倉時代。
仏教の坊主の読経を屡々聞くようになってからだろ。
和名抄で「林檎」の和名=読み方を「利宇古宇=リウコウ」と書いてる。
この「宇」の字を現代のシンガポールや台湾でメジャーな
福建省南部方言はフランス語にあるア行アイウエオの鼻の穴に
共鳴させる音で発音してたと推量出来る。
シャンゼリゼはローマ字読み。本場のフランスでは
ショーngゼリゼと聞こえる
/ɑ̃/(やや円唇): an, am, en, em – 暗い「ア」の鼻母音で、「オン」に近い。
何その中国音って😂🙊🤣
我们woman
殺されてる可能性は高いな
中国人の張政が邪馬台国に到着したことは書いてるが、卑弥呼が死んでいたことしか書いてない
仮に寿命とか病死だったならば、そう書いたはずだが「卑弥呼もって死す」としか書いてない
狗奴国との戦争で、身内に殺されたか、狗奴国の人に殺されたと考えるのが合理的だ
へぇー
中大兄皇子と藤原鎌足に殺されただろ
中学レベルの日本史くらいちょっとは勉強しろ
そもそも記述が正しいかの検証のしようがない魏志倭人伝のみがソースって時点で微妙だろ
アイヌの古語では女陰をアラハバキ、男根をクナトというらしいね
クナトは延喜式の道饗祭に出てくる神さまだな
高天之原に事始めて、皇御孫之命と称辞竟へ奉る、大八衢に湯津磐村の如く塞り坐す皇神等の前に申さく、
八衢比古・八衢比売・久那斗と御名は申して辞竟へ奉らくは
とある
高天は奈良の金剛山辺りだな
金剛山は元々高間山と呼ばれていた
近くには旧石器時代からのサヌカイトの採集地の二上山がある
縄文時代から男根の石棒が全国で見つかっており、弥生時代後期においても池上曽根遺跡から木製の男根が見つかっている
緑をアオと呼ぶのはなぜか
日本語の謎である
これはアオというのは元々広い意味だった
白黒付けないものは全てアオ
中間・半端みたいな意味だった。青っちょろいみたいなことだろうか
だから黄色ですらアオと呼んだところもあった
沖縄の古老に黄色をアオと呼んでいた記録がある
緑は最終候補に残ったものなのだろう
アイヌ語のアウは日本語の”会う””逢う”と同じ意味だが
“間”という意味もある
“逢う”というのがそもそも人々の”間”の意味なのだそう
アオの語源はアウと同じであり
アイヌ語ではそのまま表されている


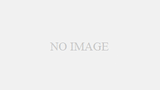
コメント